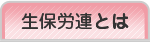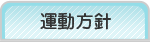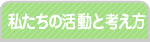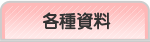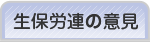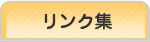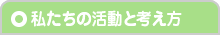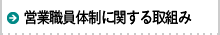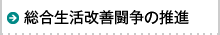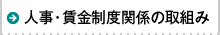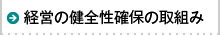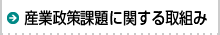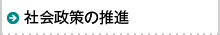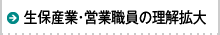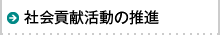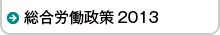(1) ワーク・ライフ・バランスに関する労使協議体制を確立する
- ワーク・ライフ・バランスの実現を推進していく上でまず何よりも重要なのは、労使が課題認識を共有化し、一丸となって取組みを進めていく土台としての労使協議体制の確立である。
- ワーク・ライフ・バランスの実現を推進していく上でまず何よりも重要なのは、労使が課題認識を共有化し、一丸となって取組みを進めていく土台としての労使協議体制の確立である。
- 本部レベルでの協議体制の構築はもとより、職場レベルにおいても、職場懇談会や衛生委員会等の場で、ワーク・ライフ・バランスに関する現状・課題や本部方針の徹底等について積極的に協議を行っていく必要がある。
- 協議にあたっては、両立支援制度の利用率や労働時間など、ワーク・ライフ・バランスに関連する具体的目標を労使で設定することも重要となる。
(2) ワーク・ライフ・バランスに関する経営トップの方針を明確化する
- ワーク・ライフ・バランスを実現する上でカギとなるのは経営者の意識や取組み姿勢である。
- トップがワーク・ライフ・バランスを明確に経営戦略に位置づけ、継続的に取組みの意義や必要性を管理職や従業員に訴えていくよう、働きかけを行うことが重要である。
(3) ワーク・ライフ・バランスに関する管理職の意識改革を行う
各種制度の利用や労働時間問題に対して直接に影響力を及ぼす管理職の意識改革は、職場風土改善の観点からも、極めて重要である。
経営トップの考え方や方針を現場の管理職に浸透させるとともに、社内の両立支援制度をしっかりと理解させるための仕組みづくり(各種研修や人事評価制度上の工夫)が求められる。
(4) ワーク・ライフ・バランスに関する組合員の意識改革を行う
ワーク・ライフ・バランスの実現に向けては、経営トップや管理職はもとより、われわれ組合員自身も進んで意識改革を行っていく必要がある。
機関誌やホームページでのアナウンスやポスター作成、セミナーの開催等を通じ、ワーク・ライフ・バランスに対する組合員の理解促進や職場風土改革を進める。
(5) 業務運営体制のチェック・見直しを行う
ワーク・ライフ・バランスの課題は様々であるが、多かれ少なかれどの課題にも関わる根本的問題として、「業務運営体制」あるいは「業務量と要員の比率」(業務量に比して要員が少なすぎる)がある。
衛生委員会をはじめとした労使協議の場を通じて、業務運営の見直しや業務スクラップ、要員配置の見直しを協議・実施し、ワーク・ライフ・バランスが実現できる体制づくりを進める。
2.両立支援制度の拡充
(6) 法を上回る育児休業制度を整備する
育児休業制度の充実は、人材獲得やとりわけ営業職員の早期離職を防ぐ上でも重要である。
制度拡充にあたっては、期間の延長だけでなく、取得回数の増加や有給化等についても積極的に協議する。
(7) 法を上回る介護休業制度を整備する
営業職員の中で最も大きな割合を占めているのは40代後半から50代の層ということもあり、組合員の介護休業に対するニーズは他産業に比べても大きいものと考えられる。
制度拡充にあたっては、期間の延長だけでなく、取得回数の増加や有給化等についても積極的に協議する。
(8) 法を上回る子の看護休暇制度を整備する
子の看護休暇は法定で「年5日、小学校就学前まで」となっているが、子供の急な発熱などにより看護が必要となる機会は多く、看護休暇制度の拡充に対するニーズは大きいものと思われる。
制度拡充にあたっては、取得日数の増加や有給化、さらには対象拡大(「対象年齢引き上げ」、「子に限らず家族全員を対象」等)についても積極的に協議する。
(9) 短時間勤務制度を整備する
育児・介護支援のためには、一定期間休業をして育児・介護に専念できる制度を整備するだけでなく、働きながら育児・介護に従事できる仕組みづくりが不可欠である。
こうした観点から、1日の労働時間を短縮する短時間勤務制度や1週間の勤務日数を削減する短日勤務制度の整備を行う。
(10) 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度や残業免除制度を整備する
従業員の就労ニーズが多様である中で、1日の労働時間を減らすことなく、育児・介護に従事できる仕組みづくりも重要となる。
こうした観点から、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げを認める制度や、残業を免除する制度の整備を行う。
(11) 時間単位での年休取得制度を整備する
年次有給休暇は両立支援の観点からも重要な制度であるが、育児や介護等に関わる所用の中には、数時間で済むものも少なくない。
そこで、子の看護休暇制度や短時間勤務制度等を補完する観点、また年休取得自体を促進する観点から、年次有給休暇を半日単位、時間単位で取得できる制度を整備する。
(12) 育児・介護を理由とした転勤免除制度や配偶者転勤制度を整備する
本人あるいは配偶者の転勤は、従業員の仕事と育児・介護の両立に深刻な影響を与える可能性がある。
そこで、育児・介護に従事する者を転勤の対象から除外する制度や、配偶者の転勤にあわせて勤務地を変更できる制度を整備する。
(13) 育児・介護手当制度を整備する
育児・介護と仕事の両立を実現する上で、休業や労働時間短縮など「働き方」に関わる支援だけでなく、金銭面での支援もまた重要となる。
育児や介護にかかる様々な費用の負担が少しでも軽減されるよう、手当支給制度を整備する。
(14) 育児・介護を理由に退職した場合の再雇用制度を整備する
育児・介護と仕事の両立支援は年々進展しているとはいえ、従業員が育児・介護を理由にやむなく退職するケースは今後も出てくるものと思われる。
育児・介護を理由に退職した従業員の再雇用制度を整備することは、人材確保の観点からも、重要である。
(15) 各種制度の利用対象者の拡大をはかる(育児・介護以外の理由)
ワーク・ライフ・バランスは、家族的責任の有無等に関わらず全ての者が主体となるべき取組みである。
組合員のニーズを踏まえつつ、休暇制度や短時間勤務制度、終業時刻の繰上げ制度、残業免除制度などの利用を、自己啓発など育児や介護以外の理由にも広げることを検討する。
3.両立支援制度の活用促進
(16) 両立支援制度の従業員への周知を徹底する
制度の充実を進めているにもかかわらず、従業員が制度の仕組みや制度の存在そのものを知らない、といったケースは意外に少なくない。
両立支援諸制度(職場復帰支援制度や人事評価上の取扱い等も含む)をわかりやすくまとめたパンフレットの作成や、制度利用者の声を集めたイントラネット上の社内コミュニティの設置等を通じ、従業員の制度に対する理解を深めることが重要となる。
(17) 職場復帰支援体制を整備する
特に休業期間が長期にわたる育児休業制度については、休業取得後の職場復帰に関する不安を取り除くことが制度の活用を促進する上で極めて重要となる。
復職前面談の実施や、社内情報の定期的な連絡、「eラーニング」の活用も含めた職場復帰支援プログラムの提供等を通じ、円滑な職場復帰に向けた支援を行うことが求められる。
(18) 両立支援制度の利用について、人事評価・職場復帰のルールを明確化する
休業制度や短時間勤務制度の利用が人事評価上どのように扱われるかは、制度の利用に大きな影響を与える問題である。
「無条件で査定を下げられる」「臨給が大幅にカットされる」「3年間昇進資格がなくなる」といったことにはならないよう、復職後の従業員のモチベーションといった点にも配慮しつつ、人事評価上のルールの明確化をはかる必要がある。
(19) 両立支援制度に関する相談窓口の設置やアンケート調査を行う
両立支援制度の運営においては、制度利用に関する組合員の疑問や不安をいかに解消していくか、また制度に対する不満や要望にどう応えていくかが大きなカギとなる。
両立支援制度の利用等に関する相談窓口の設置やアンケート調査の実施を通じ、組合員の生の声を吸い上げ、制度改善へと積極的に反映させていくことが求められる。
(20) 休業取得者等が出た場合の業務分担ルールを確立する
休業制度や短時間勤務制度等の利用を阻害する要因の1つは、自分が制度を利用することで職場に多大な迷惑をかけてしまうのではないかという懸念である。
当該職場内での分担や代替要員の配置等対応のあり方は様々であるが、業務分担の一定のルールを確立し明確化することが、制度利用促進につながると考えられる。
4.労働時間問題対策
(21) 適正な労働時間管理を徹底する
労働時間問題対策としては、「実態把握→要因分析→対策実施」のプロセスの継続が不可欠となるが、適正な労働時間管理はその基礎となる最も重要な取組みである。
労働時間の的確な把握に向けた記録方法・点検方法の改善や、「労働時間管理者」の任命等による責任体制の明確化などを推進し、労働時間管理の徹底をはかる。
(22) 労働時間実態調査を実施し、対策を労使で協議する
労働時間問題の現状を把握し改善をはかる観点から、労働時間管理の徹底がはかられていることを前提に、労働時間実態調査を実施する。
調査結果をもとに課題を洗い出し、要因を分析するとともに、労使協議の場で具体的な対策を検討する。この一連のプロセス(実態把握→要因分析→対策実施)を継続し、労働時間問題の解決をはかることが重要となる。
(23) ノー残業デーの設定やオフィスクローズを実施する
長時間労働を是正する上では、職場風土・意識改革や、残業を前提としない効率的な仕事の進め方を促す仕組みづくりも重要となる。
適正な業務運営体制が構築されていることを前提に、ノー残業デーの設定やオフィスクローズを実施し、労働時間短縮をはかる。
(24) 年次有給休暇や各種特別休暇の取得促進をはかる
労働時間の短縮を進めるにあたっては、日々の労働時間や休日労働を縮減するだけでなく、年次有給休暇や各種特別休暇の取得を促進することが重要となる。
従業員の年休取得状況をチェック・通知する仕組みづくりや、夏季および年末年始等の連続休暇取得促進運動などにより、休暇の取得率向上をはかる。